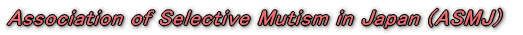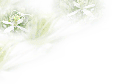 |
 |
[サイトマップ]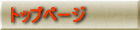 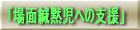 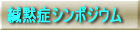 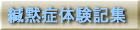 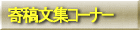 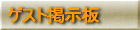 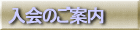 場面緘黙症の概説 書籍&リンク集
|
ごあいさつ はじめまして。私はかんもくの会の代表の弥生桜と申します。 私は場面緘黙症を経験した者です。 学校での緘黙状態が高校卒業まで治らず、そのまま大人になりました。 緘黙状態真っ只中のときももちろん苦しかったですが、大人になってからの人生も後遺症のために辛いものになりました。 私が「場面緘黙症」という言葉に初めて出会い、自分がその当事者だったことを知ったのは、高校を卒業してから十数年も経ってからのことでした。 それまで自分は誰にも理解されない異常な人間だという孤立感にずっと苛まれていましたが、緘黙症を知り、他にも同じ経験をしている人がたくさんいることを知っただけで、少なくとも孤立感はなくなりました。 しかし、場面緘黙症の後遺症そのものが解消するわけではなく、生き辛さは未だに残ったままです。 緘黙児の保護者の方々や緘黙児を受けもつ学校の先生方は、緘黙症の適切な治療方法を示す情報が非常に少ないことに困っておられるのではないでしょうか。 緘黙症の当事者であった方々は、なぜ話をできないのか周囲の理解を得られず、独りで苦しんでこられたのではないでしょうか。 私は2005年8月から個人的にブログ上で自分の場面緘黙症にまつわる体験談を書いたり問題解決のための意見を述べたりしていましたが、本当に緘黙症を巡る問題を解決するためには、実社会に働きかけを行わなければならないと考えていました。 けれども、緘黙症の後遺症を引き摺る自分が目立つ行動をすることにどうしても抵抗があり、なかなか勇気を出せないでいました。 当時、インターネット上で見つかる海外の緘黙症の専門書は何冊もありましたが、日本語で書かれた一般向けの専門書は1994年に発行された「場面緘黙児の心理と指導(河井芳文・河井英子共著/田研出版)」が一冊あるのみでした。でも、その一冊があったおかげで、緘黙症即ち自分自身を理解するのに大変役に立ちました。 しかし、それから10年以上もの間、緘黙症に特化した書籍は日本では一冊も刊行されていませんでした。 一度海外の新しい本を読んでみたいと思っていたところ、同年10月に、その2ヶ月前に発行されたばかりの緘黙症の専門書をネット上で見つけ、1500円と安かったので早速購入して読んでみました。 それはカナダの緘黙症治療の専門家たちが著した緘黙児の指導マニュアルでした。 読みすすめるにつれ、ここまで細かく指導するのかというぐらい具体的で実践的な内容であることがわかり、びっくりしました。 読み終えて、自分だけがこの内容を理解しているだけではあまりにももったいない、自分が学者だったら絶対にこの本を翻訳して広めるだろうと思いました。 私は仕事上英文を読む必要があるので、指導書の内容を理解することはできました。 しかし、それを誰にでも分かりやすい日本語に翻訳する力はありませんでした。 どうにかして、この本を一刻も早く最高品質の翻訳書として世に出せないだろうかと考えた末、翻訳、監修、出版の作業をすべて専門の人たちに任せるのが最善の方法だと結論し、そのお願いをすることぐらいなら自分でもできると思いました。 そして、上京して翻訳書制作の依頼を行いました。 入念に説明の準備をした甲斐があり、監修をお願いした武蔵丘短期大学の河井英子先生や田研出版の方々にその場で翻訳書制作のご承諾をいただきました。 この翻訳書制作の依頼を受け入れてもらえたことが私に自信を与えてくれました。 これからも自分ができることならなんでも活動をしていこうと思うようになりました。 しかし、ひとりでできることには限界があるので、数人の仲間を募って「かんもくの会」を結成し、協力し合って活動を始めました。 当会は現在、緘黙症を巡る諸問題の解決のために必要な種蒔きの活動を行っていると言えます。 これまでの主な活動の成果は次のとおりです。
以上は対外的に目立つ活動の成果ですが、このほかにも問題解決の土台作りのための活動を地道に行っています。 ところで、私は最近まで、わかっているのに緘黙症の問題をほったらかしにしている人がいるという怒りに似た気持ちをもっていて、その責任を追及する態度でいました。 しかし、活動を通じていろいろな立場の人々と関わるうちに、緘黙症が社会的に放置されている責任は誰にもないということがわかってきました。 緘黙症がほとんど問題視されない原因は、緘黙症が「他者から見て本人の深刻な実像が非常に理解しにくい」という特性をもった障害であるからです(障害という言葉は本当は使いたくありませんが…)。 周りの人たちは当事者の辛さを見て見ぬふりをしているのではなくて、本当にわからないのです。 当事者の立場の私にとって心の中でこのことを受け入れて認識を整理しなおすのは天地をひっくり返すほどの作業でした。 しかし、だからこそ、当事者が体験を語って教える必要がある。黙っていればいつまでも世の中に緘黙症の現実が知られることはない。そう思うようになりました。 これからも緘黙症を巡る問題の解決のために私たちでできることを積み重ねていきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 2009年1月13日 |